「別荘の設計が終わったら,工事はどのように始まるのかな?」
「リビングからの眺めとか,事前に確認できるのかな?」
「神主さんを呼ぶ,地鎮祭(じちんさい)はどうすれば良いのかな?」
などと,①土地の購入(借地),②建物の設計 が終わった段階で,次に具体的にすることは何か,あなたは知りたいと思いませんか?
そこで,この記事では,全くの素人で,実際に「わがまま別荘」を建設したサラリーマンである “わが坊” が,体験談に基づいて,“まま子” と一緒に解説します。
本記事では「別荘建設直前の土地の様子」と「工事の着工直前にすべき3つのこと」について,実際のわがまま別荘の写真を用いて説明していきます。
 まま子
まま子別荘の設計が終わったら,いよいよ工事が始まるのね。



その前に,現地を視察して最終確認,地鎮祭,上棟式があるよ。
- 建設前の別荘地の最終確認
- 地鎮祭の様子
- 始まった工事の着工
建設前の別荘地の最終確認





リビングからの海や山の眺めは大丈夫かしら?



建物の方角や眺望とか,建設前の最終的な現地確認は大事だよ。
建設前の土地はこんな感じ
当該の別荘地は,以前に誰かが別荘を建てて使用していたという土地ではなく,ある別荘地の原野の区画になります。したがって,購入まで自然状態のままなので,木や草が生い茂っていました。そこに,新たに別荘を建てるわけですが,その購入した土地の面積は約500坪ほどあり,かなり広いですが,平地は3分の1程度で,残りは建物が建てられないような斜面になっています。自宅の住居であれば平面の方が良いのはもちろんですが,別荘では,斜面がある方が前面が開けて眺望は良くなるので,土地の全部が平地でない方が都合が良いことも多々あります。また,当該別荘地は6m幅の舗装道路が付いており,管理人もいるので,いろいろと便利で都合が良いです。こうした条件も考えて別荘地は購入する必要があります。
特に,眺望をメインにする場合,リビングを2階にする場合は,実際の2階の高さからの眺望を実感できるように,事前に敷地内に「やぐら」を建ててもらい,景観を見ると良いです(左下写真にやぐら)。これは工務店のフトコロの大きさによりますが,これによって実際の眺望がイメージでき,リビングの間取りや窓の仕様,内装などにも良い影響が出てくるので,是非,工務店に頼んでみると良いでしょう。また,既に樹木が生えている場合は,極力切らずに,植栽の一部にするなども考えられます。余裕のある敷地で他人を気にしなくてよいこと,これがまず,わがまま別荘ライフの第一条件と言えますね。また,別荘を建てる土地の地盤が適切かどうかのボーリング調査を行います。地盤が大丈夫ということになったら,いよいよ役所に建築確認申請をしてもらうことになりますね。その後,地鎮祭です。






やぐらを設置


ボーリング調査
地鎮祭(じちんさい)の様子





地鎮祭(じちんさい)って,何をするのかしら?



工事の安全を祈願する神事だね。神主さんを呼ぶよ。
地鎮祭(じちんさい)とは?
設計事務所の設計士さんや工務店との建物の設計プランがまとまり,契約も済み,いよいよこれから土地を整地して建物の建設が始まるという直前に,地鎮祭(じちんさい)を行います。地鎮祭とは,土地を守る神様に別荘工事の無事と安全を祈願する神事です。最近では,省略されることもありますが,縁起物なので実施することが多いです。地元の神主さんを探さなければいけませんが,工務店やハウスメーカーで手配してくれることがほとんどなので,心配は無用です。実施する際には,神主さんへの謝礼,供物の準備費用などが別途掛かります。だいたい,神主さんへ「御初穂料」または「玉串料」として3万円,供物の準備費用は5万円くらいが相場でしょうか。結構費用が掛かりますが,これは建設費の一部とみなして穏便に済ませておく方がスマートです。
地鎮祭は,施主(わがまま別荘の家族)と,工事関係者(設計事務所の設計士さん,工務店の社長さん)などが参加して厳かに行われます。事前に,別荘地内に神棚が設けられ,酒,魚,昆布,野菜,果物などが供物として供えられます。野外で行いますが,椅子なども用意されるので,施主や工事関係者は,椅子に座って地鎮祭に臨みます。施主としては,敷地に「鍬(くわ)入れ」などの儀式を行い,工事の安全と無事に建物が完成できるように祈念します。もちろん,お神酒でお清めも行います。
・海の幸(タイなどの魚,昆布,スルメ)
・山の幸(大根・茄子などの野菜,りんご・みかんなどの果物)
・お米(1合) ・お塩(1合)・ お水(1合)
・お神酒(清酒)
わがまま別荘の地鎮祭
わがまま別荘では,工務店の社長さんがいつもお願いしている,神主というより山伏のようないでたちの御仁を紹介して頂き,短刀を使ったり,法螺貝(ホラガイ)を吹いたりして,非常に趣きのある地鎮祭を行いました。こういう機会はあまりないので,とても興味深く楽しむことができました。 しかし,不謹慎ながら,工務店の社長さんが言っていた通り,この古風な儀式と,のどかで清閑な別荘地に,高らかに響く,違和感あり過ぎの法螺貝の音色に,思わず笑いを堪えるのが大変でした。神聖な儀式なのにスミマセン(反省・・・)。










始まった工事の着工





地鎮祭が終われば,いよいよ工事の開始ね。
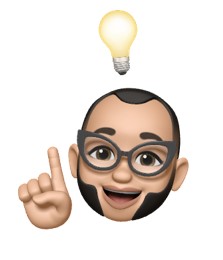
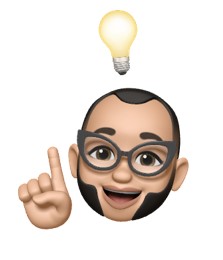
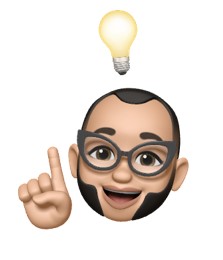
あとは,職人さんにお任せするのみです。
区画の整地
地鎮祭が終わったら,いよいよ工事の着工になりますが,まずは樹木の伐採です。全ての樹木が伐採されたら,次は大型重機による区画の整地が始まります。この作業は,基本的に工務店さんが行いますが,設計事務所の設計士さんも現地に何回も通って,設計通りに行われているかと進捗状況を確認します。もう工事が始まったら,施主であるわが坊は,何もすることはありません。ただ,無事に工事が進展するのを待つのみです。
当該の別荘地は標高800m程度なので,雪はそんなに降りませんが,冬に雪深い別荘地では,工事期間と完成予定日は重要になります。季節としては,春に完成を迎えると理想的なのですが,こればっかりは設計や建築申請なども関係してくるので,何とも言えません。設計事務所,工務店などとよく相談して着工から受け渡しまでの期間を検討しましょう。








上棟式(じょうとうしき)とは?
工事が進み,屋根を作り始める前には上棟式(じょうとうしき)を行います。「棟上げ」というのは,木材の柱で別荘の骨組みを作って,最後に屋根の一番上に「棟木」を設置する作業のことです。上棟式とは,棟上げまで工事が終わったことに感謝して,残っている工事の安全と建築後の家内安全を祈願する儀式です。地鎮祭は数名でこじんまりと行うことが多いですが,上棟式は工事関係者のほとんどすべてが参加し,大がかりに行います。昔は(今でも行うところはあります),新築の家を建てるときに,この上棟式で近隣の人たちに餅を投げたり,投げ銭をしますね。わが坊も,はるか昔の小僧の時の記憶で,近所の家の新築の上棟式に参加して,小銭やお菓子,餅などを拾ったことがありますよ。
本来は,施主が実施すべきですが,特に別荘などでは,場所も遠くなることがあり,現代では省力することが多いようです。ただし,わがまま別荘でも,わが坊は参加しませんでしたが,工務店の社長さんに音頭を取ってもらい,職人さん(現場監督や棟梁さんなど)などに食事とご祝儀と食事などを振舞ってもらいました。上棟式でご祝儀や食事代などの費用を合計すると,人数にもよりますが,10~30万円はかかるようです。工務店によっては,ドンブリ勘定で上棟式の費用が含まれる場合もあるようですが,確認しておくと良いでしょう。地鎮祭と同様に,縁起ものなので慣例に従った方が良いです。






まとめ
「工事の着工直前にすべき3つのこと」は,①別荘地の最終確認,②地鎮祭,③上棟式です。この記事では,この3つの神事を中心に工事直前の雰囲気をご紹介しました。
・別荘地の最終確認
・地鎮祭の様子
・始まった工事の着工
この中でも特に重要なのが,「別荘地の最終確認」と「地鎮祭」ですね。計画はすでに出来上がっているので,ここに来て計画を変えることはかなり無理がありますから,あくまで「最終確認」ですね。上棟式は不在で工務店にお任せしても良いかもしれませんが,地鎮祭は必ず行う必要があります。もちろん,そのぶん費用も掛かってしまいますが,お祝い事,縁起物なので,滞りなくスムーズに行いたいものです。
上棟式も大事な神事ではありますが,特に別荘では工務店にお願いして,不参加が多いようです。もちろん,不参加でもご祝儀やお食事代は出さないといけませんね。
地鎮祭,そして上棟式と,ここまでくれば,あとはもう工務店の職人さんにお任せするだけです。数か月後のわがまま別荘の完成を夢見て,あともう一息です。このように,別荘のプランニング以外にも,いろいろと行うことがありますが,それもこれも,わがまま別荘の完成に必要な手順です。
こうした観点をしっかりと理解しておけば,あとは待つだけです。何といっても,「自分の別荘」を所持するということ自体が別荘ライフの醍醐味であり,自分名義の別荘で,自分の好きなように思いっきりわがままな別荘ライフを満喫する,そこに意義を見出すのが「わがままで快適な別荘ライフ」です。皆さんも素敵な別荘ライフを始めてみませんか。

コメント